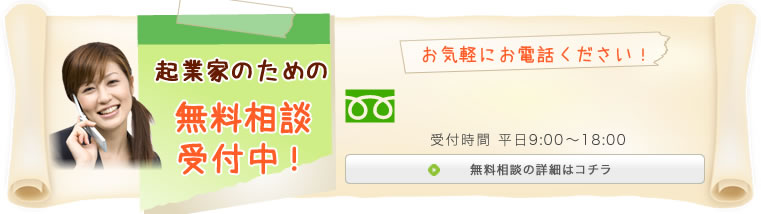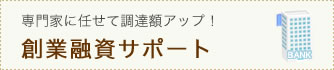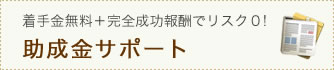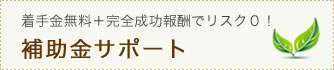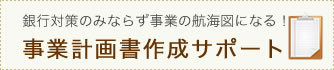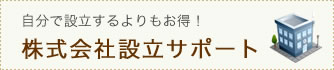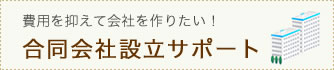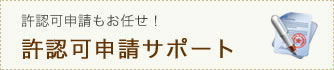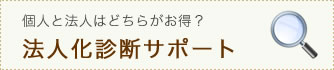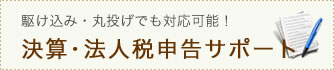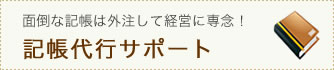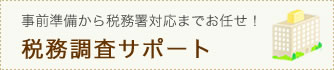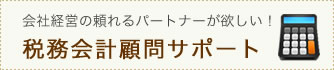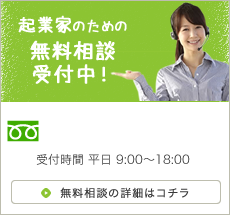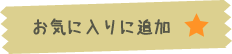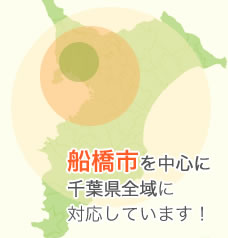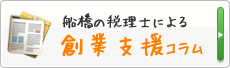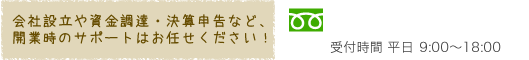起業におすすめの融資は?創業融資の種類と成功へのポイントを徹底解説
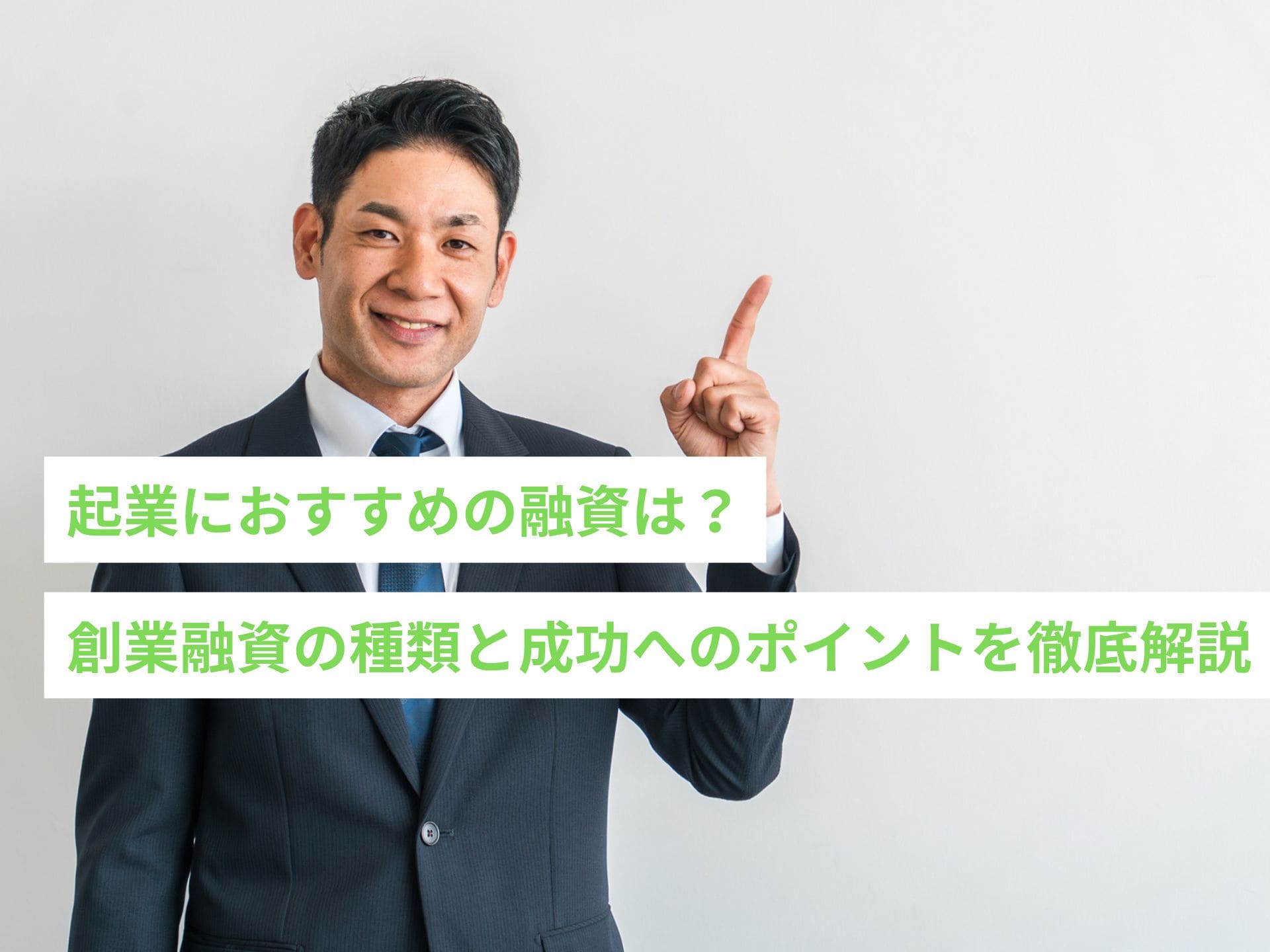
「起業したいけれど、資金が足りない…」「融資を受けたいけど、どこに相談すればよいかわからない」、そんな不安を抱えている方は少なくありません。特に初めての起業では、自己資金だけでスタートするのは難しく、公的な創業融資制度の活用が成功の鍵となります。
中でも、日本政策金融公庫の新規開業資金や、自治体の制度融資などは、無担保・無保証人で借りられるケースも多く、初めての起業家にとって強い味方となる存在です。しかし、どの制度が自分に合っているのか、どのように申し込めばよいのかは、専門的な知識がないと判断が難しいのが現実です。
本記事では、起業時におすすめの融資制度の種類や違い、利用のメリット・デメリット、審査通過のポイントをわかりやすく解説します。さらに、税理士による創業融資サポートの活用方法についてもご紹介。資金面の不安を解消し、安心して事業をスタートしたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
起業時の資金調達にはなぜ融資の活用がおすすめ?
起業には、設備費・人件費・広告費・仕入れ資金など、まとまった初期費用が必要です。しかし、自己資金だけでこれらすべてをまかなうのは難しいというのが現実です。特に初めての起業では、収入の見通しが立ちにくく、資金面の不安から一歩を踏み出せない方も少なくありません。
そこで活用したいのが、国や自治体が用意している「創業融資制度」です。創業融資とは、これから事業を始める方や、開業から間もない方に向けて提供される公的な融資制度で、無担保・無保証人で借りられるケースが多いのが特長です。
特に注目されているのが、日本政策金融公庫の「新規開業資金」。この制度では、創業時に必要な運転資金や設備資金を、低金利かつ長期返済で借りられるため、開業後のキャッシュフローに余裕が生まれます。
また、創業融資を受けることで、金融機関との取引実績を早い段階で構築でき、今後の追加融資や資金調達の際にも信用がつきやすくなるというメリットもあります。
このように、創業融資は資金面のリスクを抑えつつ、経営の自由度を高める有効な手段です。返済義務はあるものの、制度内容を正しく理解し、事業計画をしっかり立てて活用すれば、起業の大きな後押しとなるでしょう。
初めての起業で利用できる主な融資制度
起業時の資金調達にはさまざまな方法がありますが、初めて起業する方でも比較的利用しやすいのが公的な融資制度です。ここでは、代表的な制度として、日本政策金融公庫の融資制度と、自治体が実施する制度融資についてご紹介します。
日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」
日本政策金融公庫(略称:公庫)は、政府が100%出資する金融機関で、創業者支援に特化した融資制度を提供しています。その中でも特に注目したいのが、「新規開業・スタートアップ支援資金」です。
この制度は、これから事業を始める方や開業からおおむね7年以内の方を対象にしており、無担保・無保証人での借入も可能です。また、女性・若者・シニア起業家向けの優遇制度も用意されており、対象となればさらに低金利で利用できます。
融資限度額は原則7,200万円(うち運転資金は4,800万円)で、十分な資金調達が見込めます。さらに、金利も民間のビジネスローンに比べて低めに設定されており、返済期間も長期にわたる(最長20年)ため、初期の資金繰りに余裕を持たせることができます。
事業計画書の提出は必須ですが、しっかり準備すれば、実績のない創業者でも資金を確保できる可能性があります。
信用保証協会付き融資(自治体の制度融資)
都道府県や市区町村などの自治体では、地元の中小企業・創業者向けに「制度融資」を設けており、その多くが信用保証協会との連携によって実施されています。
この制度では、自治体が指定した金融機関を通じて融資を受けることができ、信用保証協会が保証人の代わりとなってくれるため、金融機関側の審査ハードルが下がる仕組みになっています。
また、自治体によっては、利子補給(利子を一部補助する制度)や保証料の一部負担といった支援が受けられることもあります。たとえば、「実質無利子で融資を受けられる期間がある」といった優遇措置もあり、起業初期の資金負担を大きく軽減できるのが魅力です。
ただし、制度融資は自治体・金融機関・信用保証協会の三者が関わるため、書類準備や手続きが複雑になりやすく、融資実行までの期間も長めになる傾向があります。スケジュールに余裕を持ち、事前に専門家に相談しておくことをおすすめします。
当事務所では、日本政策金融公庫の融資申請はもちろん、制度融資の利用支援も行っております。詳しいご相談をご希望の方は、「無料相談はこちら」よりお気軽にお問い合わせください。
創業融資を利用するメリット
起業時の資金調達において、創業融資は非常に有力な選択肢です。補助金や出資など他の手段と比べても、公的融資には独自のメリットが多数存在します。ここでは、創業融資を活用することで得られる主なメリットを詳しく見ていきましょう。
1. 無担保・無保証で借りられる可能性がある
日本政策金融公庫の「新規開業資金」など、一部の創業融資では担保や保証人を必要としない制度が用意されています。これは、まだ資産や信用実績が少ない起業家にとって、大きな支援となります。
通常の融資では、自己所有の不動産や第三者保証が求められるケースが多い中、創業融資は創業者の計画と熱意が重視されるため、より挑戦しやすい仕組みとなっています。
2. 金利が低く、返済期間も長い
創業融資の多くは、金利が年2%前後と低水準に設定されています(※金利は制度や時期により異なります)。さらに、設備資金なら最長20年、運転資金でも最長7年程度の返済期間が認められることもあります。
そのため、月々の返済額を抑えながら資金を確保でき、開業直後のキャッシュフローに余裕を持たせることが可能です。
3. 自己資金の少なさを補える
多くの起業家が悩むのが、自己資金の不足です。創業融資を活用すれば、自己資金に数倍する金額の融資を受けられる可能性があります。これは、より大きな事業計画の実現や、広告・採用など初期投資の充実につながります。
たとえば、自己資金が200万円しかなくても、600万円〜800万円の資金を調達することも可能です(※審査内容や計画によって異なります)。
4. 創業後の信用実績になる
創業融資を受け、計画通りに返済を続けることは、金融機関との信用構築につながる重要な実績になります。これは、将来的に追加融資を受ける際や、新たな取引先との契約時にも大きなアドバンテージとなります。
「起業時に公庫から融資を受けている」という事実は、外部からの信頼度を高め、経営者としての信用力向上にもつながります。
5. 資金繰りの安定化と精神的安心
十分な資金を確保できているかどうかは、起業後の精神的な安定にも大きく影響します。開業後すぐに赤字になるケースは多く、そこで手元資金が枯渇すると、事業継続が困難になることもあります。
創業融資によってあらかじめ十分な運転資金を準備しておけば、短期的な売上のブレにも冷静に対応でき、事業の成長に集中できるでしょう。
これらのメリットを活かすためにも、早めの準備と正確な事業計画の立案が重要です。もし一人での準備に不安がある場合は、専門家による無料相談をご活用ください。
創業融資を利用する際のデメリット・注意点
創業融資は多くのメリットがある一方で、注意すべき点やデメリットも存在します。制度を正しく理解せずに利用すると、資金繰りや信用に悪影響を与える可能性もあります。ここでは、創業融資の代表的なリスクと注意点について解説します。
1. 融資には必ず「返済義務」がある
当然のことですが、融資で得た資金は借金であり、月々の返済と利息の支払いが発生します。仮に売上が思うように伸びなかったとしても、返済は止められません。
そのため、融資額を決める際には事業計画に基づいた現実的な収支シミュレーションを行い、「返済可能な額かどうか」を必ず確認しておくことが重要です。
2. 希望した融資額を受けられないことがある
創業融資は自己資金の割合や事業計画の実現可能性によって審査されます。そのため、希望した融資額よりも低い金額しか借りられない場合があります。
たとえば、「自己資金ゼロ」で1,000万円を希望するなど、無理のある申請は否決される可能性が高く、審査通過率も下がってしまいます。
融資希望額と自己資金のバランス、計画の妥当性は、慎重に設計する必要があります。
3. 審査に時間と手間がかかる
創業融資を申し込むには、事業計画書や見積書などの書類作成が必要です。さらに、公庫や自治体の制度融資では面談やヒアリングも行われるため、申請から融資実行までに1ヶ月程度かかることもあります。
開業時期が決まっている場合は、融資スケジュールを逆算して早めに準備を開始することが大切です。
4. 返済が経営を圧迫する可能性も
たとえ少額の融資でも、毎月の返済負担が積み重なると、キャッシュフローに影響します。特に創業直後は売上が安定せず、支出ばかりが増える傾向があるため、想定以上に資金繰りが厳しくなるケースもあります。
「借りられる額」ではなく「返せる額」を基準にすることが、失敗しない創業融資のコツです。
5. 融資後も経営責任が重くなる
融資を受けることで、計画通りに経営を進めなければならないプレッシャーも生まれます。また、公的制度の中には、資金の使途報告や経過報告を求められるケースもあります。
返済計画に沿った経営判断や、想定外のトラブルに備えた資金管理体制が求められるため、起業後も継続的な経営意識が必要になります。
これらのデメリットは、事前準備と専門家のサポートによって軽減することが可能です。初めての創業融資に不安を感じる場合は、税理士による無料相談の活用もご検討ください。
創業融資の審査に通過するためのポイント
創業融資は非常に有利な資金調達手段ですが、審査に通過しなければ融資は実行されません。特に創業段階では、実績がない分、事業計画の完成度や自己資金の有無が大きく評価されるため、事前の準備が重要です。ここでは、審査を突破するために押さえておきたいポイントを解説します。
1. 実現可能性の高い事業計画書を用意する
創業融資の審査で最も重視されるのが、事業計画書の内容です。売上見込みや経費の根拠が曖昧な計画では、信用性を欠き、審査に通りづらくなります。
市場調査に基づいた数値、具体的な収支計画、競合との差別化ポイントを明確に記載し、創業者の経験・スキルもアピールできる構成にしましょう。審査担当者に「この事業なら成功しそうだ」と感じてもらうことが大切です。
2. 自己資金を一定額準備しておく
自己資金は信用力の証明となります。目安としては、開業資金の2~3割程度の自己資金があると、融資審査で有利に働きます。
自己資金が少ないと、「事業に対する本気度が低い」「返済能力に不安がある」と判断されやすくなります。創業までに時間がある場合は、できるだけ貯蓄を増やしておくことが望ましいです。
3. 創業に関連する実務経験や資格を示す
創業者のこれまでの職務経験や保有資格は、審査において事業遂行能力の裏付けとして重要視されます。
たとえば飲食店を開業する場合、飲食業界での勤務経験や調理師免許の有無がアピール材料となります。経験やスキルの有無が、事業の実現可能性を高める根拠となるため、事業計画書や面談時にしっかり伝えましょう。
4. 面談での受け答えを丁寧に行う
日本政策金融公庫などでは、融資申請後に審査担当者との面談(ヒアリング)が実施されます。この際、事業内容を簡潔かつ明確に説明できることが重要です。
想定される質問(「なぜ起業するのか」「事業の強みは何か」「売上見込みの根拠は?」など)には、事前に答えを用意しておきましょう。また、話し方や態度も評価の対象となるため、誠実で前向きな印象を与えることを意識しましょう。
5. 専門家のサポートを活用する
創業融資の準備は、自分ひとりでは不安や不備が出やすいものです。そこでおすすめなのが、税理士や中小企業診断士などの専門家に相談することです。
事業計画書のブラッシュアップや、面談対策、融資申請書類のチェックなど、専門的な目線でアドバイスを受けることで、通過率が大幅に向上します。
当事務所では、日本政策金融公庫の創業融資に強い税理士が、無料相談にて対応しております。これから起業を考えている方、申請準備に不安がある方は、お気軽にご相談ください。
融資以外の資金調達方法も検討しよう
創業時の資金調達といえば「融資」が王道ですが、それ以外にも事業に必要な資金を集める手段は複数存在します。資金の出どころを多様化することで、リスクの分散や資金繰りの安定にもつながります。ここでは、創業融資以外に検討すべき代表的な資金調達方法を紹介します。
1. 補助金・助成金の活用
補助金・助成金は返済不要の資金であり、うまく活用すれば初期投資の大きな助けになります。国や自治体が実施する創業支援制度の中には、開業費用の一部を補助してくれるものがあります。
たとえば、「小規模事業者持続化補助金」や「創業促進補助金」などがあり、広告宣伝費や設備投資費などに活用できます。ただし、申請には事前の準備や申請書類の作成、審査通過が必要となるため、専門家に相談しながら進めると安心です。
2. 出資を受ける(エクイティファイナンス)
将来性のあるビジネスモデルを持っている場合、エンジェル投資家やベンチャーキャピタル(VC)からの出資を受けるという手段もあります。これは返済の必要がない代わりに、会社の株式の一部を提供する形で資金を調達する方法です。
出資を受ければ、財務的な負担なく大きな資金を得られる可能性がありますが、経営に一定の関与を受けることになるため、方向性の共有や信頼関係が重要です。主にIT系やスタートアップ志向の強い業種で利用されやすい手段です。
3. クラウドファンディング
近年では、クラウドファンディングを活用した資金調達も一般的になっています。インターネット上で自社のビジネスプランや商品・サービスを公開し、賛同者から小口資金を集める仕組みです。
特に、商品開発や地域活性化、社会貢献型のビジネスは共感を得やすく、広く資金を集められる可能性があります。また、資金調達と同時に認知度向上や見込み客の獲得にもつながるのが大きなメリットです。
4. 親族・知人からの借入
創業期には、親族や信頼できる知人からの資金援助や借入もひとつの選択肢です。金融機関よりも柔軟な条件で資金を得られる可能性があり、信用関係が築けていれば、返済期間や金利の面でも融通が利くことがあります。
ただし、口約束ではなく金銭消費貸借契約書を作成し、金銭トラブルを避けるようにしましょう。あくまでビジネスとしての対応を徹底することが信頼関係維持のポイントです。
5. 売掛債権や資産の活用
事業開始後は、売掛債権を担保に資金を得る「ファクタリング」や、不要な設備・不動産を売却して資金に充てるなどの方法も検討できます。これらは主に運転資金が急に必要になった際の対応策となりますが、資金繰りの柔軟性を高める選択肢として知っておくと便利です。
複数の手段を組み合わせて活用するのが理想
創業時には、融資だけでなく、補助金・出資・クラウドファンディングなどを組み合わせて総合的に資金計画を立てることが成功への鍵です。それぞれにメリット・デメリットがありますので、事業内容や経営者の強み・リスク耐性に応じた使い分けが求められます。
どの方法が適しているか判断に迷う場合は、専門家による無料相談を通じてアドバイスを受けることをおすすめします。
起業しやすい年齢・タイミングはいつ?
「起業するには若い方がいい?」「定年後でも遅くない?」と、年齢について不安を抱える方も少なくありません。しかし、結論から言えば、起業に年齢の制限はなく、何歳からでもチャレンジ可能です。大切なのは年齢ではなく、「準備が整っているかどうか」です。
年齢制限は基本的にない
日本では、法的には15歳以上であれば会社設立の代表者になることも可能であり、年齢による起業の制限はありません。近年では、学生起業や60代以上のシニア起業も増えており、人生のあらゆるステージで「起業」という選択肢が開かれているのが現状です。
起業する人が多い年代とは?
統計によると、30代〜40代が起業のボリュームゾーンです。これは、社会経験や人脈、ある程度の貯蓄ができてくる時期であり、リスク管理とチャレンジ精神のバランスが取りやすいことが理由として挙げられます。
また、20代の若手起業家は、柔軟な発想やITリテラシーを活かしたスタートアップが多く、50代〜60代のシニア起業家は、長年の業界経験を活かした独立開業が多く見られます。
年代別のメリット・注意点
- 20代:新しい発想力と行動力が強み。一方で資金や経験不足に注意。
- 30〜40代:社会経験・資金・人脈などが揃いやすく、バランスのとれた起業タイミング。
- 50代〜:業界知識や信用力が高い反面、体力・健康面やIT対応力の強化が課題。
創業融資にも年齢制限はない
日本政策金融公庫の創業融資なども年齢に関係なく申請可能です。むしろ、若者・シニア起業家向けの優遇制度(例:「女性、若者/シニア起業家支援資金」)が用意されており、年齢をハンデではなく強みに変える制度も存在します。
大切なのは「タイミング」より「準備の質」
起業の成功に年齢は関係ありません。最も大切なのは、しっかりとした事業計画・資金計画が立てられているかという点です。たとえ若くても準備が不十分では資金調達も困難になり、逆にシニアでも準備が整っていればスムーズに起業できるでしょう。
年齢を理由に不安を感じている方も、まずは現実的な計画と行動を始めることが大切です。一歩を踏み出すタイミングは、「今、準備できるかどうか」で決まります。
「自分の年齢で融資が通るか不安…」という方は、税理士による無料相談をご利用いただくことで、個別の状況に応じたアドバイスが可能です。
よくある質問(FAQ)
Q1. 創業融資は誰でも申し込めるのですか?
原則として、これから起業する方や開業後おおむね7年以内の方であれば申請可能です。法人・個人事業主を問わず利用できます。ただし、過去の信用情報に問題がある場合や、明確な事業内容・資金計画が立てられていない場合は、審査で不利になる可能性があります。
Q2. 自己資金が少なくても融資は受けられますか?
自己資金が少なくても融資を受けることは可能ですが、目安としては創業資金の1割以上は自己資金で準備することが望ましいとされています。自己資金がゼロの場合は、融資希望額が大幅に減額されたり、審査に落ちることもあります。
Q3. 起業前でも融資を申し込むことはできますか?
はい、創業前でも事業計画が固まっていれば申請可能です。実際に、日本政策金融公庫では「開業予定日」が明確であれば、法人登記や個人事業開始前でも融資申込を受け付けています。ただし、開業を具体的に示す資料(店舗の賃貸契約書、見積書など)が求められる場合があります。
Q4. 審査にはどれくらい時間がかかりますか?
日本政策金融公庫の場合、申請から融資実行まで2~4週間程度が目安です。書類の不備があったり、面談日程が遅れた場合はさらに時間がかかることがあります。制度融資(自治体の融資)を利用する場合は、金融機関・信用保証協会・自治体とのやり取りが加わるため、1ヶ月以上かかることもあります。
Q5. 融資を受けると、どのような返済が発生しますか?
融資には毎月の元本返済+利息支払いが発生します。例えば、公庫の創業融資では年利2%前後で、返済期間は最長で20年(設備資金)や7年(運転資金)などが設定されています。据置期間(元本返済を一定期間免除)が設けられることもあり、資金繰りに配慮した設計が可能です。
Q6. 自分に合った融資制度がわかりません。どうすればいい?
ご自身で判断が難しい場合は、専門家に相談することをおすすめします。当事務所では、創業融資支援に特化した税理士が無料相談を行っており、あなたの事業内容や資金ニーズに応じた最適な融資制度をご提案いたします。無料相談はこちらからどうぞ。
まとめ(結論)
起業において資金調達は避けて通れない重要なステップです。自己資金だけで事業を始めるのが難しい場合、公的な創業融資を活用することで、大きなチャンスを得ることができます。
特に日本政策金融公庫の「新規開業資金」や、自治体の制度融資は、無担保・無保証人でも利用できる可能性があり、低金利・長期返済という好条件が揃っています。
ただし、融資を受けるには事業計画や自己資金、面談対応などの準備が不可欠です。融資には返済義務があるため、資金の使い方や借入額の妥当性も慎重に見極める必要があります。
また、融資だけに頼らず、補助金やクラウドファンディング、親族からの支援など多角的な資金調達方法を検討することで、より安定したスタートを切ることができます。
起業の適齢期はありません。大切なのは、「今の自分がどれだけ準備できているか」です。そして、その準備を効率的かつ確実に進めるためには、専門家のサポートを活用することが成功への近道になります。
起業を真剣に考えている方は、無料相談などを活用しながら、確かな資金計画とともに第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。
まずは専門家に相談して、起業の第一歩を踏み出しましょう
「どの融資制度が自分に合っているのか分からない」「事業計画の作り方が不安」「金融機関とのやり取りに自信がない」──そんなお悩みをお持ちの方は、一人で悩まずに専門家に相談することが成功への近道です。
山野淳一税理士事務所では、創業融資の支援に力を入れており、初回のご相談は無料で承っています。事業内容や資金ニーズを丁寧にヒアリングし、融資審査に通るための事業計画書作成、面談対策、必要書類の準備まで、トータルでサポートいたします。
これまでに多数の創業支援実績があり、日本政策金融公庫や自治体制度融資への申請も多数サポートしています。初めての起業でも安心してご相談いただけます。
「資金面の不安を解消して、安心して開業したい」という方は、ぜひ一度、無料相談フォームからお問い合わせください。
あなたの夢のスタートを、私たちが全力でサポートいたします。
船橋の税理士による創業支援コラムの最新記事
- 千葉で建設業の会社設立を進める流れをわかりやすく開設
- 千葉で建設業に強い税理士をお探しなら山野淳一税理士事務所にご相談ください
- 千葉県の建設業許可についてわかりやすく解説。必要なケース・種類・要件・申請の流れをまとめて解説
- 船橋市で建設業許可を取るには?必要・不要の判断から要件、費用、申請の流れまでわかりやすく解説
- 初心者でも安心!株式会社設立代行の選び方とポイント
- 会社設立の相談を無料でできるところはどこ?おすすめ相談先について解説
- 銀行口座の開設は会社設立後に!必要書類や金融機関の種類について解説
- 会社設立される方へ。税理士に相談した方が良い理由と選び方のポイント
- 浦安市で会社設立するなら?手続きの流れ・必要書類・創業融資まで徹底解説
- 千葉市で会社設立するなら山野淳一税理士事務所にご相談を!累計200社以上のサポート実績!
- 柏市の会社設立で押さえるべきポイントは?注意点や対処法も解説
- 松戸市で会社設立!手順やおすすめの方法を解説
- 船橋市最安の会社設立サポート!実質負担3万4千円。船橋会社設立・開業相談オフィス(運営:山野淳一税理士事務所)
- 鎌ヶ谷市でマネーフォワードに強い税理士を探すなら?対応できる事務所の選び方と失敗しないポイント
- マネーフォワードに強い税理士を習志野市で探すなら?失敗しない選び方とおすすめ事務所を解説
- 柏市でマネーフォワード対応の税理士を探すなら?選び方と導入メリットを徹底解説
- 浦安市で「マネーフォワード」を導入するなら?経理効率化と税務サポートに強い税理士の選び方
- 松戸市でマネーフォワード対応の税理士をお探しの方へ。クラウド会計に強い山野淳一税理士事務所
- 船橋市でマネーフォワードに強い税理士をお探しなら山野淳一税理士事務所にご相談ください
- 八千代市でマネーフォワード対応の税理士を探すなら?クラウド会計に強い専門事務所の選び方
- 習志野市での会社設立の進め方。株式会社・合同会社の比較や費用相場、創業融資までやさしく解説
- 市川市でマネーフォワードに強い税理士なら山野淳一税理士事務所にご相談下さい
- 八千代市で会社設立するための流れや必要な費用を解説
- 市川市で会社設立するには?専門家へ依頼するメリットや注意点を解説
- 会社設立時の融資審査を突破するポイントと対策
- 千葉市における起業の魅力と支援制度をわかりやすく解説
- 千葉県にはどんな創業支援制度があるの?まとめて解説!
- 会社設立は誰に頼むべき?依頼できる専門家についてわかりやすく解説
- 会社設立における事業目的とは?重要性や具体例を解説
- 法人設立から創業融資を受けるまでの流れを解説!失敗しないポイントとは?
- 起業時に銀行から融資を調達する方法とは?注意点やポイントを解説
- 会社設立時に銀行から融資は受けられる?制度融資やプロバー融資、おすすめ金融機関について解説
- 起業時におすすめの創業融資4選と成功するためのポイント
- 創業融資にコンサルは必要?メリット・デメリットを解説
- 会社設立の手続きの流れと設立にかかる期間を徹底解説
- 会社設立時の借入に日本政策金融公庫がおすすめな理由
- 会社設立を税理士に相談するメリットとは?
- 千葉の税理士による無料相談窓口のご案内。どんなことが相談できる?
- 千葉で開業!融資を受ける際に気を付けるべきこととは?
- 会社設立の資金集めはどうする?自己資金を用意する方法についてご紹介
- 日本政策金融公庫の審査から融資の流れとは?税理士がわかりやすく解説
- 船橋で経理代行はどこに依頼すればいい?ポイントや探し方を解説!
- 千葉銀行の法人向け融資について解説!用途別や業種別に制度をご紹介
- 千葉県の商工会で受けられる融資を解説!マル経融資の内容やメリットとは?
- 千葉市で日本政策金融公庫の融資を受けたい方へ。千葉支店の情報や融資申請のポイントを解説
- 船橋の日本政策金融公庫はどこにある?融資を受けるポイントも解説!
- 船橋で税理士にご相談したい方へ。無料相談窓口のご案内
- 船橋で税理士の費用はどのくらい?山野淳一税理士事務所が選ばれるポイントとおすすめな理由
- 千葉で起業の相談に乗ってもらえる支援制度情報
- 千葉で飲食店を開業するには?流れや押さえたいポイントを解説!
- 千葉で建設業を開業するには?流れや注意点を解説!
- 千葉で美容室やサロンを開業するには?費用の相場や流れを解説!
- 船橋市で起業の手続きや創業融資の相談ができる制度をご紹介!
- 会社設立は自分でできる?つまづきやすい3つの注意点
- 柏市の起業で利用可能な相談窓口や優遇制度について
- 津田沼で起業する際に相談できる場所のご紹介
- 松戸の起業で相談できる場所と支援サービスについて
- 浦安で起業したい人に役立つ相談会や勉強会はある?
- 市川で起業について相談!利用できる支援制度とは
- 習志野で起業!相談できる制度や創業支援について
- 船橋で会社設立と融資について専門家へ相談するメリットとは
- 船橋で会社設立する際の費用
- 船橋で起業についての相談先を探す際のポイント
- 営業権償却 平成29年度税制改正により月額計算
- 東日本大震災復興特別貸付
- 創業時の自己資金の範囲
- 創業融資の申し込みに必要な書類
- 日本政策金融公庫の創業融資ための要件 2
- 日本政策金融公庫の創業融資ための要件 1
- 日本政策金融公庫を利用した創業融資について
- 【創業支援コラム】20150902 会社設立時の資本金
- 【創業支援コラム】20150901 会社実印
サポートメニュー一覧
資金について相談したい!
会社設立について相談したい!
経営・税務会計について相談したい!
新着情報
-
2026/01/25
-
2026/01/18
-
2026/01/14
-
2026/01/07
-
2025/12/28