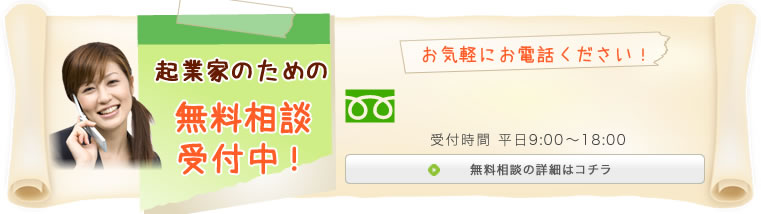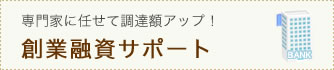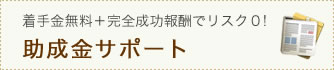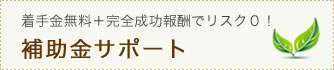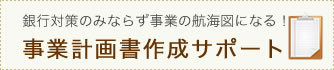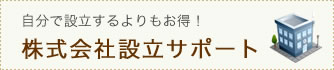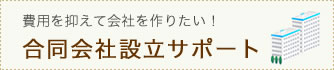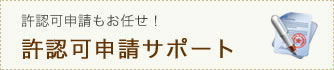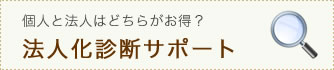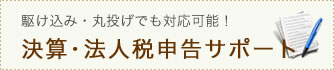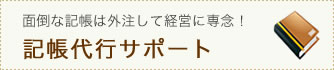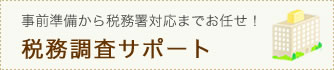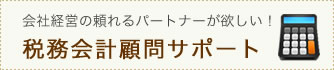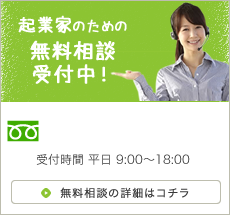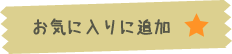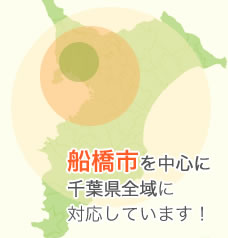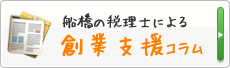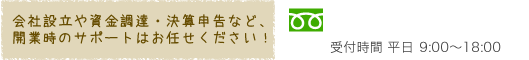八千代市で会社設立するための流れや必要な費用を解説

会社設立は、事前設計(会社形態・商号・本店所在地・事業目的・資本金・決算月)を固め、定款作成・認証(株式会社のみ)・設立登記を経て、税務・社会保険等の各種届出へと進むのが基本の流れです。電子定款を用いることで収入印紙代が不要になるなど、コストや手間を抑える選択肢もあります。いずれも制度や様式に沿って進める必要があり、書類の不備や届出漏れは後戻りの原因になりがちです。
本記事では、これから八千代市で会社設立をする方のために、株式会社/合同会社の比較、費用とスケジュールの目安、よくある落とし穴と対策、創業融資をはじめとする創業期の支援の活用ポイント、そして設立後すぐに整えるべき会計・税務の初期設計まで、最短ルートで失敗を避けるためのチェックリストとともに解説します。八千代市での立地や契約形態(自宅・賃貸・バーチャルオフィス等)を選ぶ際の注意点についても、一般的な確認事項として触れていきます。
八千代市で会社設立を始める前に決める6つのこと
スムーズな会社設立は、「事前設計」が大切です。
1)会社形態の選び方(株式会社 or 合同会社)
日本で一般的な選択肢は株式会社と合同会社です。
設立コスト・意思決定の柔軟性・将来の資金調達の想定を基準に比較します。
| 比較観点 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 定款認証 | 公証人役場で認証が必要 | 認証不要 |
| 登録免許税(目安) | 資本金の7/1000(最低15万円) | 資本金の7/1000(最低6万円) |
| 意思決定の柔軟性 | 機関設計に応じて運用(取締役1名でも設立可の非公開会社が一般的) | 内部自治が柔軟(原則として社員全員が業務執行権、定款で調整可) |
| 対外説明のしやすさ | 株式制度があり、出資・持分の説明が明快 | 少人数・小回り重視の形態として広く普及 |
| 利益配分 | 原則は持株比率に応じて配当 | 出資比率と異なる柔軟な配分が可能(定款等で定める) |
こんな人は株式会社向き/合同会社向き
-
株式会社向き:将来の資金調達や人材採用を見据えたい/株式を前提に設計したい
-
合同会社向き:設立・維持コストやスピードを重視/意思決定をシンプルにしたい
電子定款を用いれば、定款に貼付する印紙税4万円は不要です(紙で作成・提出する場合は課税)。
2)商号(社名)・本店所在地・事業目的
商号:登記上は同一住所・同一商号でも登記自体は可能とされていますが、混同リスクや商標権侵害の可能性があるため、類似調査(商標・登記・ドメイン)の実施が安全です。
本店所在地:自宅・賃貸・バーチャルオフィスいずれも制度上は選択可能。ただし賃貸契約・管理規約での使用可否や、業種によっては許認可・用途地域の制約があり得ます。
事業目的:具体性・適法性・営利性がポイント。将来展開の見込みも含め、過不足のない文言に整えましょう。
目的の書き方の基本例
-
「〇〇に関する企画、開発、制作、販売およびコンサルティング」など、実態に即した包括表現を組み合わせる
-
公序良俗に反するものや許認可が不要な表現に留める(必要な場合は許認可取得後に運用)
3)資本金・出資者(社員)・役員構成
資本金:法令上の下限はありません(1円でも設立可)。ただし運転資金・信用力・各種審査を考えると、事業計画に見合う水準を設定するのが実務的です。
出資者・役員:株式会社は取締役1名で設立可能(一般的な非公開会社の場合)。合同会社は社員(出資者)1名で設立可、原則は全社員に業務執行権があり、定款で代表社員や業務執行社員を定めて運用します。
よくあるつまずき
-
資本金を極端に低くして早期の資金ショートを招く
-
役割分担が曖昧で意思決定が遅延する(定款・社内規程で明確化)
4)決算月(事業年度)
決算月は自由に設定できます(初年度は設立日から1年以内で区切るのが一般的)。
繁忙期の回避・キャッシュフロー・在庫棚卸・税負担の平準化を考慮して決めると、事務負担のピークを避けやすくなります。
5)公告方法と機関設計(株式会社中心)
定款には公告方法(官報・新聞・電子公告など)を定めます。電子公告はコスト面の利点がある一方、ウェブサイトの継続的な閲覧可能性等の要件に配慮が必要です。
また株式会社では、取締役会の設置有無や監査役の要否など、規模・株主構成に応じた機関設計を検討します(小規模・非公開なら取締役1名でシンプル運用が一般的)。
6)実務の初期設計(口座・印章・ドメイン等)
設立後に滞りなく営業を開始するため、事前に以下を準備しておくとスムーズです。
-
事業用口座の開設準備:事業計画書、取引先の概要、ウェブサイトなど事業実態を説明できる資料
-
会社印(実印・銀行印・角印):契約・金融実務での使用が一般的
-
ドメイン・コーポレートサイト・コーポレートメール:信用力と審査対応の基盤に
-
会計処理の方針・科目・証憑運用:設立直後からの記帳ルールを明確化
手数料や様式・制度は見直されることがあります。実際の手続き前に最新の公式情報をご確認ください。
目的文言のチェックや決算月・機関設計のご相談は、初回無料で個別に整理します。
ステップ別|設立手続きの全体像とチェックリスト
会社設立の流れは大きく「定款作成」→「定款認証(株式会社のみ)」→「設立登記申請」→「税務・社会保険の届出」という手順で進みます。ここでは、それぞれのステップで必要な準備や注意点を整理します。
定款作成(電子定款を活用すれば印紙代不要)
定款には商号・本店所在地・目的・資本金・決算月・公告方法など、会社の基本情報を記載します。
株式会社の場合は「発行可能株式総数」など株式に関する規定も必須です。
紙で作成すると収入印紙代4万円が必要ですが、電子定款を用いれば不要になります。
定款認証(株式会社のみ)
株式会社の場合は公証人役場での定款認証が必須です。
認証時には定款・発起人の印鑑証明・本人確認書類・委任状などを準備します。合同会社は認証不要です。
設立登記申請(法務局)
設立登記は会社設立の最重要ステップです。登記を行って初めて法人格が成立します。
必要書類は以下の通りです。
-
登記申請書
-
定款
-
発起人の同意書・就任承諾書
-
資本金の払込証明書
-
印鑑届出書
登録免許税は株式会社:資本金の7/1000(最低15万円)、合同会社:資本金の7/1000(最低6万円)です。
法人印・証明書類の取得
登記完了後は、法人印鑑証明書・登記事項証明書を取得します。これらは銀行口座開設や各種契約に必須です。
銀行口座開設のポイント
法人口座開設には事業実態の説明資料が求められるケースがあります。事業計画書や契約書、会社ホームページなどを準備すると審査がスムーズです。
税務署・地方自治体への届出
設立後すぐに税務署や都道府県税事務所、市区町村役場への届出が必要です。代表的なものは以下の通りです。
-
法人設立届出書
-
青色申告承認申請書
-
給与支払事務所等の開設届出書
-
源泉所得税の納期の特例の承認申請書(条件該当時)
これらを期限内に提出しないと、青色申告の適用ができないなどの不利益を受ける可能性があります。
社会保険・労働保険の手続き(従業員を採用する場合)
従業員を雇用する場合、次の手続きが必要です。
-
年金事務所:健康保険・厚生年金保険の新規適用届
-
労働基準監督署:労災保険の保険関係成立届
-
ハローワーク:雇用保険適用事業所設置届
注意:提出期限や必要書類は状況によって異なります。最新の法務局・税務署・年金事務所の案内を必ず確認してください。
書類作成や届出に不安がある方は、専門家に依頼することで時間とリスクを大幅に削減できます。
詳しくはこちら(山野淳一税理士事務所の無料相談)
費用の目安とスケジュール(株式会社/合同会社の比較)
会社設立には「登録免許税」「定款作成・認証費用」「証明書取得費用」などの初期コストがかかります。また、設立完了までのスケジュールも、準備状況や会社形態によって変わります。ここで目安を押さえておくことで、資金計画や事業スタートのタイミングを見誤らずに済みます。
初期費用の内訳(目安)
| 項目 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 資本金の7/1000(最低15万円) | 資本金の7/1000(最低6万円) |
| 定款認証費用 | 約5万円(公証人手数料) | 不要 |
| 定款印紙代 | 紙の場合4万円(電子定款なら不要) | 同左 |
| 証明書取得費 | 数千円(登記事項証明・印鑑証明等) | 数千円(同上) |
実際の総費用は、株式会社で約20〜25万円程度、合同会社で約6〜10万円程度が一般的な目安です。ここに専門家報酬を加えるとさらに上乗せになりますが、手戻りを防ぎ確実に進めたい場合は有効な選択肢です。
スケジュールの目安
設立準備から登記完了までの期間は、事前準備の進み具合や形態選択によって異なります。一般的な流れは以下の通りです。
-
事前準備(商号・目的・資本金・役員決定):1〜2週間
-
定款作成・認証(株式会社):数日〜1週間
-
登記申請から完了まで:1〜2週間程度
-
銀行口座開設・届出一式:1〜2週間程度
スムーズに進めば、最短1ヶ月前後で事業スタートが可能です。ただし、創業融資や助成金の申請を並行する場合は事業計画書の作成に時間がかかることもあります。
費用・期間を抑えるコツ
-
電子定款を利用して印紙代を節約する
-
事前準備(商号調査・目的文言・役員構成)を整えてから書類作成に進む
-
定款テンプレートやチェックリストを活用し、ミスを減らす
-
専門家に依頼して登記・届出を一括代行してもらい、時間を節約
ご予算やスケジュールに合わせた費用シミュレーションを初回無料でご案内しています。
よくある落とし穴と未然防止チェック
会社設立は一度の手続きで終わるものではなく、設立後の運営にも直結する判断や届出が含まれます。ここでは、起業時に多い失敗例とその防止策を整理します。
事業目的が狭すぎて将来の変更が必要に
定款に記載する事業目的が限定的すぎると、新規事業を始める際に定款変更(株主総会決議・登記)が必要になるケースがあります。
将来の展開を見据えて、包括的かつ具体的な文言を盛り込むのが安全です。
資本金“1円”の落とし穴
法律上は1円から会社設立が可能ですが、実際には信用力の低下や早期の資金ショートを招きやすいリスクがあります。
融資や取引先との契約を考えると、事業計画に見合った資本金を設定することが大切です。
住所利用の規約違反(賃貸・管理規約・用途地域)
本店所在地を自宅や賃貸マンションに設定する場合、賃貸借契約やマンション管理規約で事業利用が禁止されているケースがあります。
また、業種によっては用途地域の制限を受ける可能性もあるため、事前確認が必須です。
口座審査での説明不足
法人口座開設では事業実態を示す資料が求められることが多いです。
事業計画書、契約予定先との資料、会社ホームページなどを用意し、事業の具体性と継続性を説明できる状態にしておきましょう。
届出漏れ(青色申告・源泉・地方税・社保・労保)
設立後には税務署・都道府県税事務所・市区町村・年金事務所・労基署・ハローワークへの届出が必要です。
特に青色申告承認申請を期限内に提出しないと、翌期まで適用が受けられず、税務上の損失につながる可能性があります。
チェックリスト活用:手続きの抜け漏れを防ぐには、ステップごとのチェックリストを活用するのが有効です。設立直後は業務が立て込みがちなので、「何を・いつまでに・どこへ」を見える化しておきましょう。
個別の状況に合わせて必要な届出・資本金の設定・事業目的文の確認をチェックします。
八千代市ならではの検討ポイントと支援の活用
会社設立の手続きは全国的に共通ですが、立地や地域の支援制度によって成功率やスタート時の資金繰りに差が出ることがあります。八千代市で会社設立を行う際に押さえておきたいポイントを整理します。
立地・許認可の確認(用途地域・業種規制の基本)
本店所在地や店舗を構える場合は、用途地域の規制や業種ごとの許認可に注意が必要です。たとえば飲食業や建設業など、一部業種は事前に所轄官庁の許可や届出が求められます。
また、自宅や賃貸物件を本店所在地にする場合、管理規約や契約条件で「事務所利用不可」とされていないかを必ず確認しましょう。
創業期の情報収集と支援窓口の活用
八千代市内で起業する場合、商工会議所やよろず支援拠点といった公的機関を活用することで、事業計画のブラッシュアップや資金調達に関するアドバイスを受けられます。
また、国の機関である日本政策金融公庫は、創業融資の代表的な相談先です。審査には事業計画書や資金繰り表の提出が求められるため、早めの準備が欠かせません。
創業融資を並走で進める流れ
設立手続きと並行して創業融資の申請を進めると、資金不足に悩まずにスタートを切れます。ポイントは以下の通りです。
-
事業計画の具体性:売上予測の根拠、顧客ターゲット、競合との差別化を明示する
-
資金計画の正確さ:開業資金・運転資金・返済計画をバランスよく示す
-
自己資金の比率:全体の資金計画に占める自己資金割合は信用性に直結
設立直後に口座残高がほぼゼロという状況は融資審査で不利になります。
設立と融資の準備を同時並行で行うことが、創業初期の安定経営につながります。
補足:八千代市を含む千葉県内では、起業支援補助金・助成金が募集されるケースもあります。時期や条件は変動するため、最新情報は市の公式サイトや商工会議所で確認しましょう。
創業融資の審査に通りやすい事業計画書の作成支援や、地域の支援制度のご案内も行っています。
設立後すぐにやるべきこと(運営フェーズの土台づくり)
会社を設立したら終わりではなく、設立直後からの運営設計がその後の経営を大きく左右します。ここでは、起業後すぐに取り組むべき重要なポイントを解説します。
会計・税務の初期設計
設立直後から記帳のルールや科目設定を整えておくことで、確定申告や決算での手戻りを防げます。
領収書や請求書は必ず事業用口座・カードと紐付けし、経費区分を明確にしておくことが重要です。
また、会計ソフトを導入し、科目を統一しておくと効率的です。
インボイス制度・消費税の選択
2023年10月から始まったインボイス制度により、取引先から「適格請求書発行事業者」への登録を求められるケースが増えています。
設立1期目は原則として消費税は免税事業者ですが、取引先との関係や仕入税額控除を考慮して登録を検討する必要があります。
契約書・約款・個人情報の管理
取引を始める前に、基本契約書や取引条件書を準備しておきましょう。
特にITや小売業では、プライバシーポリシー・利用規約の整備が信用性の向上につながります。
個人情報の取扱いに関しては、法令遵守と顧客信頼の両面から初期段階で整えることが大切です。
資金繰り表とキャッシュマネジメント
設立初期は資金の出入りが不安定になりやすいため、資金繰り表を作成して先々の支出を見える化しましょう。
特に社会保険料・源泉所得税の納付は忘れやすい項目です。
定期的にキャッシュ残高を確認し、支払期日の前に資金不足に陥らない仕組みを作ることが重要です。
助成金・補助金の情報収集
八千代市や千葉県では、時期に応じて創業支援補助金や雇用関連助成金が募集されることがあります。
これらは申請期限が短いことも多いため、定期的に市や商工会議所の情報を確認しておくとチャンスを逃しません。
ワンポイント:「設立したばかりだから後回し」と考えがちな分野ほど、後から修正が効きにくいのが実情です。会計・税務・資金管理を最初から整えることで、安心して事業に集中できます。
記帳代行・年次決算・税務顧問の設立直後から使えるサポートプランをご用意しています。
自分でやる?専門家に任せる?
会社設立は自分で進める方法と専門家に依頼する方法があります。それぞれにメリットとデメリットがあり、状況によって最適な選択肢は異なります。ここでは、両者を比較して検討できるよう整理します。
自力で設立する場合
メリット:費用を抑えられる/手続きを学べる
デメリット:時間がかかる/記載ミスや届出漏れのリスクが高い
-
電子定款の作成や法務局への登記も自分で可能。ただし「記入不備で登記を差し戻される」ケースも珍しくない。税務署・年金事務所・労基署など複数の窓口へ個別に対応する必要がある。
専門家に依頼する場合
メリット:手間と時間を削減できる/確実性が高い
デメリット:専門家報酬が発生する
-
登記書類や定款を正確に作成してもらえる。税務署や自治体への届出書類をまとめて代行してもらえる。設立後の会計・税務・社会保険まで継続サポートを受けやすい。
比較表
| 観点 | 自力設立 | 専門家依頼 |
|---|---|---|
| 費用 | 安い(登録免許税など実費のみ) | 報酬分の費用が追加 |
| 時間・手間 | 調査・作成・届出に多くの時間が必要 | 大幅に削減できる |
| リスク | 書類不備や届出漏れのリスク大 | 経験豊富な専門家によりリスク低減 |
| その後のサポート | 原則なし(自分で対応) | 顧問契約などで継続支援を受けやすい |
任せる範囲のカスタマイズ例
専門家に依頼する場合でも、全てを丸投げする必要はありません。ニーズに応じて以下のように選択可能です。
-
定款作成・登記のみ依頼(最低限のリスク回避)
-
税務署・自治体届出まで依頼(届出漏れ防止)
-
創業融資サポートも依頼(資金調達と並走)
-
設立後の会計・給与計算まで包括契約(長期的な安心)
選び方のポイント:「時間を優先するか」「費用を優先するか」「安心感を優先するか」で判断すると、自分に合った方法が見つかります。
山野淳一税理士事務所では、ご希望に応じて必要な範囲だけサポートするプランをご用意しています。
モデルケースでイメージ|八千代市×小規模スタート
実際の流れをイメージするために、業種ごとに想定されるモデルケースを見てみましょう。具体例を知ることで、費用・スケジュール・手続き内容の全体像が掴みやすくなります。
IT受託業 × 合同会社 × 資本金300万円
ケース概要:自宅を本店所在地とし、フリーランスから法人化を目指すパターン。主にシステム開発やWeb制作を受託する事業を想定しています。
費用:登録免許税6万円+電子定款作成実費+証明書類取得費数千円程度。
スケジュール:準備から登記完了まで2〜3週間前後。
初月のToDo:
-
合同会社の定款作成(電子定款で印紙代を節約)
-
設立登記申請(必要書類一式を法務局へ提出)
-
法人用銀行口座開設(取引先との契約に備える)
-
税務署への届出(法人設立届出書・青色申告承認申請など)
-
インボイス登録の要否を確認(取引先要件に応じて判断)
飲食店舗業 × 株式会社 × 採用前提
ケース概要:八千代市内に店舗を構え、複数の従業員を採用して飲食店を運営するパターン。
費用:登録免許税15万円+定款認証費用約5万円+証明書類取得費数千円。
スケジュール:物件契約・許認可手続きと並行しながら設立を進めるため、1〜2ヶ月程度を想定。
初月のToDo:
-
株式会社の定款作成と公証人認証
-
設立登記申請(発起人・役員就任承諾書など含む)
-
飲食店営業許可の取得(保健所に申請)
-
従業員採用に伴う社会保険・労働保険の適用手続き
-
資金繰り表の作成(家賃・人件費・仕入費用を考慮)
ポイント:業種や事業規模によって、必要な許認可・費用・スケジュールは大きく変わります。とくに飲食業や建設業などは許可が必須なので、会社設立と同時に申請準備を進める必要があります。
あなたの業種や事業計画に合わせて最適な設立手順や必要書類を整理いたします。
FAQ(よくある質問)
会社設立を検討する方から寄せられるよくある質問をまとめました。基本的な疑問を事前に解消しておくことで、安心して手続きを進めることが可能になります。
自宅を本店にできる?
制度上は自宅を本店所在地として登記可能です。ただし、賃貸契約やマンションの管理規約で「事務所利用不可」とされている場合は違反となる可能性があります。事前に契約内容を必ず確認しましょう。
電子定款のメリットは?
電子定款を利用すると、紙の定款で必要な収入印紙代4万円が不要になります。さらに、オンラインで作成・認証が可能なため、時間とコストを節約できます。
決算月はいつにすべき?
決算月は自由に設定可能ですが、以下の観点で検討すると良いです。
-
繁忙期を避ける:事務処理の負担を分散できる
-
税金対策:売上の状況に応じて期末をコントロールできる
-
業種特性:在庫が多い業種は棚卸のしやすい時期に設定
創業融資は設立と同時進行できる?
はい、設立手続きと並行して創業融資の準備を進めることは可能です。
ただし、融資審査では事業計画書や資金繰り表が求められるため、早めに書類を整えておくとスムーズです。
インボイス制度には登録すべき?
設立直後は免税事業者となるのが一般的ですが、取引先から登録を求められるケースがあります。売上規模や仕入税額控除の有無を踏まえ、登録の可否を判断してください。
注意:制度や提出期限は改正される可能性があります。必ず最新の公式情報を確認してください。
個別の事情によって最適な判断は変わります。迷ったときはお気軽にご相談ください。
まとめ
八千代市で会社設立を成功させるには、事前の設計・正確な手続き・設立後の運営体制づくりが欠かせません。
とくに会社形態の選択(株式会社か合同会社か)、事業目的や資本金の設定、決算月の決定は、その後の税務や資金調達、取引先からの信用に直結する大切なポイントです。
また、設立後は税務署・自治体への届出や社会保険・労働保険の手続き、さらには会計・資金繰り・インボイス制度対応など、短期間で多くの準備が必要となります。これらを怠ると、青色申告の適用漏れや資金ショートといったリスクにつながるため注意が必要です。
さらに、八千代市や千葉県内では創業融資や助成金制度が活用できるケースもあるため、制度を知らないまま進めて損をしないよう、最新情報をチェックしておくことも重要です。
結論:「設立手続きを正確に進める」だけでなく、その後の運営を見据えた初期設計が成功の鍵です。ひとりで抱え込むのではなく、専門家に相談することで時間・コスト・リスクを最小化できます。
山野淳一税理士事務所では、会社設立から創業融資・税務顧問までワンストップ支援を行っています。
初回相談は無料ですので、安心してご活用ください。
船橋の税理士による創業支援コラムの最新記事
- 初心者でも安心!株式会社設立代行の選び方とポイント
- 会社設立の相談を無料でできるところはどこ?おすすめ相談先について解説
- 銀行口座の開設は会社設立後に!必要書類や金融機関の種類について解説
- 会社設立される方へ。税理士に相談した方が良い理由と選び方のポイント
- 浦安市で会社設立するなら?手続きの流れ・必要書類・創業融資まで徹底解説
- 千葉市で会社設立するなら山野淳一税理士事務所にご相談を!累計200社以上のサポート実績!
- 柏市の会社設立で押さえるべきポイントは?注意点や対処法も解説
- 松戸市で会社設立!手順やおすすめの方法を解説
- 船橋市最安の会社設立サポート!実質負担3万4千円。船橋会社設立・開業相談オフィス(運営:山野淳一税理士事務所)
- 鎌ヶ谷市でマネーフォワードに強い税理士を探すなら?対応できる事務所の選び方と失敗しないポイント
- マネーフォワードに強い税理士を習志野市で探すなら?失敗しない選び方とおすすめ事務所を解説
- 柏市でマネーフォワード対応の税理士を探すなら?選び方と導入メリットを徹底解説
- 浦安市で「マネーフォワード」を導入するなら?経理効率化と税務サポートに強い税理士の選び方
- 松戸市でマネーフォワード対応の税理士をお探しの方へ。クラウド会計に強い山野淳一税理士事務所
- 船橋市でマネーフォワードに強い税理士をお探しなら山野淳一税理士事務所にご相談ください
- 八千代市でマネーフォワード対応の税理士を探すなら?クラウド会計に強い専門事務所の選び方
- 習志野市での会社設立の進め方。株式会社・合同会社の比較や費用相場、創業融資までやさしく解説
- 市川市でマネーフォワードに強い税理士なら山野淳一税理士事務所にご相談下さい
- 市川市で会社設立するには?専門家へ依頼するメリットや注意点を解説
- 会社設立時の融資審査を突破するポイントと対策
- 起業におすすめの融資は?創業融資の種類と成功へのポイントを徹底解説
- 千葉市における起業の魅力と支援制度をわかりやすく解説
- 千葉県にはどんな創業支援制度があるの?まとめて解説!
- 会社設立は誰に頼むべき?依頼できる専門家についてわかりやすく解説
- 会社設立における事業目的とは?重要性や具体例を解説
- 法人設立から創業融資を受けるまでの流れを解説!失敗しないポイントとは?
- 起業時に銀行から融資を調達する方法とは?注意点やポイントを解説
- 会社設立時に銀行から融資は受けられる?制度融資やプロバー融資、おすすめ金融機関について解説
- 起業時におすすめの創業融資4選と成功するためのポイント
- 創業融資にコンサルは必要?メリット・デメリットを解説
- 会社設立の手続きの流れと設立にかかる期間を徹底解説
- 会社設立時の借入に日本政策金融公庫がおすすめな理由
- 会社設立を税理士に相談するメリットとは?
- 千葉の税理士による無料相談窓口のご案内。どんなことが相談できる?
- 千葉で開業!融資を受ける際に気を付けるべきこととは?
- 会社設立の資金集めはどうする?自己資金を用意する方法についてご紹介
- 日本政策金融公庫の審査から融資の流れとは?税理士がわかりやすく解説
- 船橋で経理代行はどこに依頼すればいい?ポイントや探し方を解説!
- 千葉銀行の法人向け融資について解説!用途別や業種別に制度をご紹介
- 千葉県の商工会で受けられる融資を解説!マル経融資の内容やメリットとは?
- 千葉市で日本政策金融公庫の融資を受けたい方へ。千葉支店の情報や融資申請のポイントを解説
- 船橋の日本政策金融公庫はどこにある?融資を受けるポイントも解説!
- 船橋で税理士にご相談したい方へ。無料相談窓口のご案内
- 船橋で税理士の費用はどのくらい?山野淳一税理士事務所が選ばれるポイントとおすすめな理由
- 千葉で起業の相談に乗ってもらえる支援制度情報
- 千葉で飲食店を開業するには?流れや押さえたいポイントを解説!
- 千葉で建設業を開業するには?流れや注意点を解説!
- 千葉で美容室やサロンを開業するには?費用の相場や流れを解説!
- 船橋市で起業の手続きや創業融資の相談ができる制度をご紹介!
- 会社設立は自分でできる?つまづきやすい3つの注意点
- 柏市の起業で利用可能な相談窓口や優遇制度について
- 津田沼で起業する際に相談できる場所のご紹介
- 松戸の起業で相談できる場所と支援サービスについて
- 浦安で起業したい人に役立つ相談会や勉強会はある?
- 市川で起業について相談!利用できる支援制度とは
- 習志野で起業!相談できる制度や創業支援について
- 船橋で会社設立と融資について専門家へ相談するメリットとは
- 船橋で会社設立する際の費用
- 船橋で起業についての相談先を探す際のポイント
- 営業権償却 平成29年度税制改正により月額計算
- 東日本大震災復興特別貸付
- 創業時の自己資金の範囲
- 創業融資の申し込みに必要な書類
- 日本政策金融公庫の創業融資ための要件 2
- 日本政策金融公庫の創業融資ための要件 1
- 日本政策金融公庫を利用した創業融資について
- 【創業支援コラム】20150902 会社設立時の資本金
- 【創業支援コラム】20150901 会社実印
サポートメニュー一覧
資金について相談したい!
会社設立について相談したい!
経営・税務会計について相談したい!
新着情報
-
2025/12/28
-
2025/12/21
-
2025/12/14
-
2025/12/07
-
2025/12/06