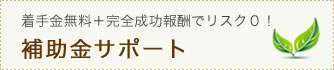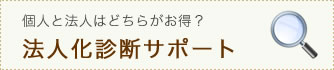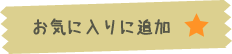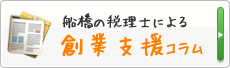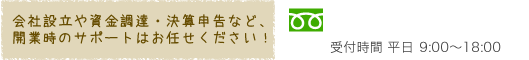タワーマンションによる相続税節税の裁判事例
節税目的で取得した不動産の評価について、評価通達によらないことが相当と認められる
「特別の事情」があるとして、その時価は鑑定評価額であるとされた事例です
下にある、評価額と現実の取引価格との間に著しい乖離の判断が難しいところですが、半分以下
の場合には乖離ということになっております。
こちらはTAINS コードZ888-2395からの引用になります。
概要は以下になります。
本件は、被相続人Bの相続人である亡A、控訴人C及び控訴人Dが、Bの相続(本件相続)により
取得した財産の価額を財産評価基本通達(評価通達)の定める評価方法により評価して本件相続に
係る相続税の申告をしたところ、処分行政庁が、本件相続に係る相続財産のうち一部の土地及び建物
(本件不動産)の価額について評価通達の定めにより評価することが著しく不適当と認められるとして、
亡A、控訴人C及び控訴人Dに対し、相続税の各更正処分等をしたことから、亡A、控訴人C及び
訴人Dがこれを不服として、その取消しを求める事案である。亡Aは、原審の口頭弁論終結後判決言
渡前に死亡したところ、同人の妻である控訴人○が亡Aの訴訟手続を受継した。
2 控訴人らは、どのような場合に評価通達に定める評価方法以外の方法によって財産の価額を評価するかについての基準が明らかではなく、各更正処分は、国民の租税に対する予測可能性を著しく失わせる不当なものであり、租税法律主義の趣旨に反し、評価通達6の適用に関する行政庁の裁量の範囲を著しく逸脱するものであると主張する。しかし、相続税法22条は、特別の定めのあるものを除くほか、相続等により取得した財産の価額は当該財産の取得の時における時価によると定めているところ、この時価については当該財産の客観的交換価値をいうものと解され、課税要件は明確である。租税平等主義の観点に照らして、租税負担の実質的な公平を著しく害することが明らかな場合についてまで、評価通達の定めにより評価すべきものではないし、そのような場合について評価通達の定めによらないで個別に財産を評価したとしても租税法律主義に違反するということはできない。
3 なお、亡Aは、相続税を減少させる目的で本件不動産を相続開始時の直前に15億円で購入しているのであるから、評価通達の定めによる評価額と現実の取引価格との間に著しいかい離があることは十分認識していたというべきであり、現実の取引価格によって課税されることについて予測可能性がなかったということはできない。
4 控訴人らは、評価通達の定めによる評価額と実際の取引価格との間にかい離がある例は多数存在するから、かい離の存在は本件通達評価額によらないことが相当と認められる特別の事情を基礎づける事実にはなり得ないと主張する。しかし、本件不動産の本件通達評価額は、本件鑑定評価額の2分の1にも達しておらず、金額にして5億円以上も少ないから、そのかい離の程度は著しいといわざるを得ないところ、本件全証拠によってもこのような著しいかい離の存在が一般的であると認めることはできない。
5 控訴人らは、相続に際し、節税対策をとることは当然であり、本件被相続人が節税目的で本件不動産を購入したとしても、そのことが特別の事情を基礎づけるものではないと主張する。しかし、本件不動産の購入及びそのための借入れは3億円を超える相続税の圧縮効果を生じさせるものであるところ、亡Aがかかる相続税の圧縮を認識し、これを期待して15億円を借り入れ、本件不動産を購入したことは、租税負担の実質的な公平という観点から見た場合、本件通達評価額によらないことが相当と認められる特別の事情を基礎づける事実に当たるというべきである。
6 控訴人らは、被相続人が本件不動産を購入したのは不動産賃貸業の一環であり、相続税対策のためではないと主張する。しかし、亡Aが、本件相続に係る相続税の負担を軽減する方法について千葉銀行Q支店の担当者らに相談し、その方策として、紹介された本件不動産を購入することになった経緯は、証拠から優に認められるところであり、本件不動産の購入が相続税対策のためであったことは明らかである。
7 よって、控訴人らの請求をいずれも棄却した原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからいずれも棄却することとする。
相続税の最新記事
サポートメニュー一覧
資金について相談したい!
会社設立について相談したい!
経営・税務会計について相談したい!
新着情報
-
2025/06/08
-
2025/05/03
-
2025/05/02
-
2025/04/23
-
2025/03/27