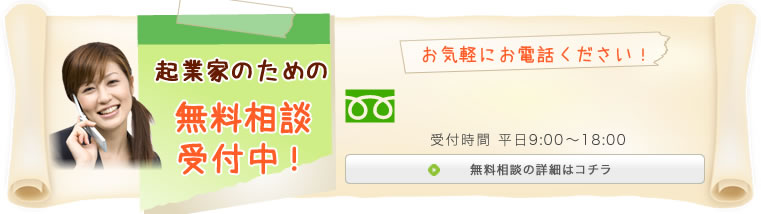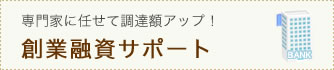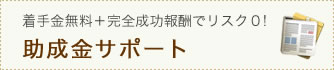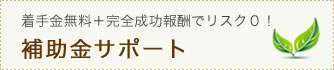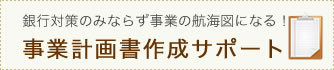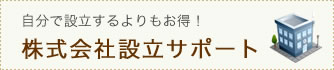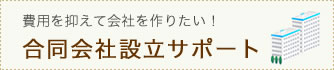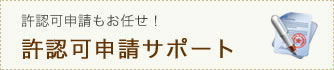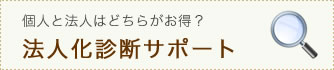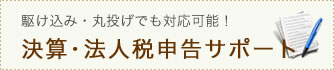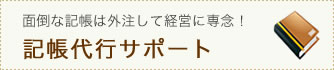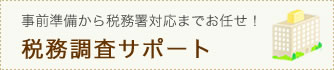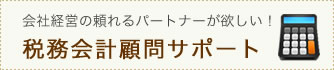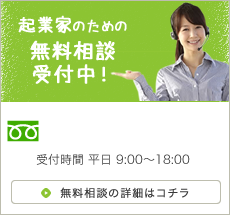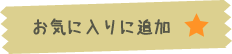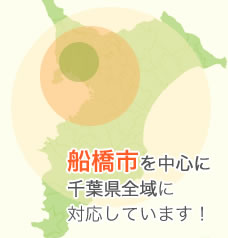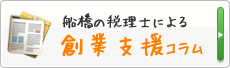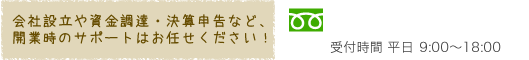設備などの除却・廃棄を利用した節税方法
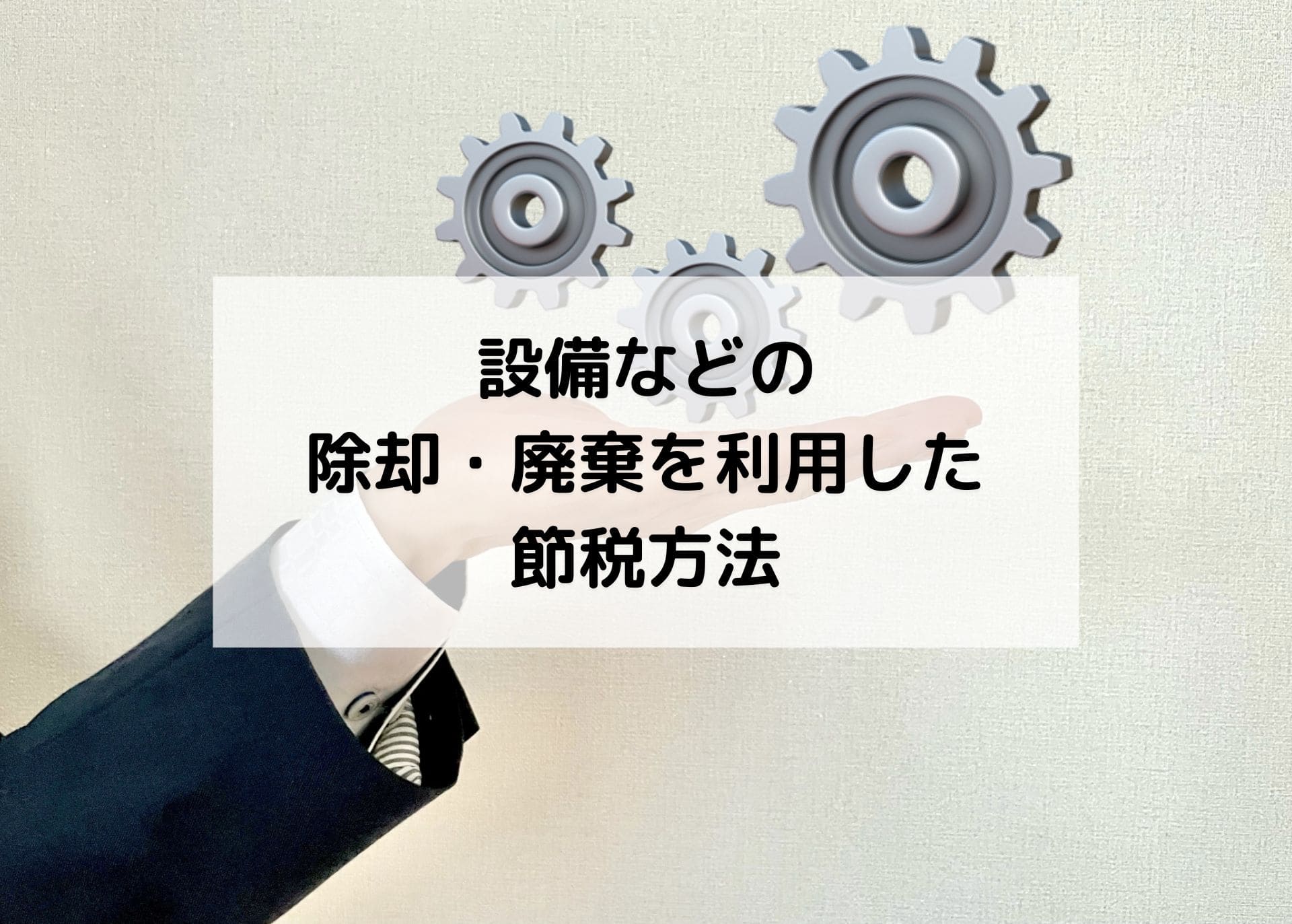
使用しなくなった設備や老朽化した資産を除却・廃棄することは、単なる資産整理にとどまらず、節税効果を得る重要な手段となります。法人が保有する設備や固定資産は、使用し続けている限り減価償却により徐々に価値が減少していきますが、除却や廃棄を行うことで、未償却残高を損金として計上することが可能になります。これにより、課税所得を減少させることで法人税負担を軽減することができます。
ここでは、設備や資産の除却・廃棄を利用した節税の仕組みや具体的な手続き、注意点について詳しく解説します。
1. 設備などの除却・廃棄とは
1-1. 除却とは
「除却」とは、企業が保有する設備や固定資産を使用しなくなった場合に、その資産を帳簿上から除去することを指します。
・老朽化や故障により使用不可能となった設備
・生産能力の向上や業態変更に伴い不要になった設備
・法的制約や安全性の問題で使用できなくなった資産
→ 除却により、その資産の未償却残高(帳簿価額)を損失として計上できるため、課税所得を減少させることが可能になります。
1-2. 廃棄とは
「廃棄」は、使用不能となった資産や価値がなくなった設備を実際に解体・処分することを指します。
・工場の機械設備を解体して廃棄
・事務所用のパソコンや家具を廃棄
・店舗の什器を取り壊して撤去
→ 廃棄を行った時点で、その資産の帳簿価額(未償却残高)を損金として計上できるため、課税所得の減少につながります。
2. 除却・廃棄を利用した節税効果
設備や資産を除却・廃棄することで、税務上の「損金」として計上できるため、法人税の負担を軽減する効果があります。
2-1. 未償却残高を損金として計上
除却・廃棄により、資産の帳簿価額(未償却残高)を損失として計上できるため、課税所得を減少させることが可能です。
【例】
・資産取得額:1,000万円
・減価償却累計額:700万円
・未償却残高:300万円
→ 資産を除却・廃棄した場合、300万円を損失計上可能
→ 法人税率33%の場合、300万円 × 33% = 990万円の節税効果
2-2. 撤去費用も損金として計上可能
廃棄や除却を行う際には、設備の撤去費用や解体費用が発生する場合があります。
これらの費用も損金(経費)として計上可能であるため、課税所得をさらに減少させる効果があります。
【例】
・未償却残高:300万円
・解体費用:50万円
→ 損失として計上できる額:300万円 + 50万円 = 350万円
→ 節税効果:350万円 × 33% = 115万円
2-3. 有姿除却の活用
有姿除却とは、設備が実際には存在しているが使用不能と判断し、帳簿上から除去する処理方法です。
・工場で使用していない老朽化した設備を有姿除却
・将来使う予定のない機械設備を帳簿から除去
➡ 実際に廃棄しなくても、未償却残高を損失計上できるため、節税効果が期待できます。ただし、有姿除却の場合には、使用不能を証明するために手間がかかりますので、安易に利用するのはやめましょう。
2-4. 建物や設備を取り壊す場合の特例
老朽化した建物や設備を取り壊した場合、取り壊し費用も損金として計上可能です。また、建物や設備の取り壊し後の跡地を事業用資産として再利用する場合、固定資産税や都市計画税の軽減措置が適用されるケースもあります。
➡ 例:耐用年数が終了した倉庫を取り壊して跡地を駐車場として利用
→ 取り壊し費用を損金計上
3. 除却・廃棄を行う際の注意点
🔸 資産台帳の管理を徹底
・除却・廃棄を行う資産は資産台帳に正しく記録されている必要がある
・資産台帳に記載がない場合、損失計上が認められない可能性がある
🔸 未償却残高の確認
・未償却残高がある資産のみ損失計上可能
・償却が完了した資産は除却しても損失として計上できない
🔸 撤去費用の正確な把握
・撤去や解体にかかった費用を正確に記録
・明細書や領収書を保管
🔸 税務調査への対応
・除却・廃棄の処理が不適切な場合、税務調査で否認される可能性
・除却・廃棄に関する契約書、写真、領収書などの証拠を準備
5. まとめ
設備や資産の除却・廃棄は、企業にとって重要な節税手段となります。除却・廃棄を行うことで、未償却残高を損金として計上し、法人税負担を軽減できます。また、撤去費用や解体費用も損金として認められるため、適切な処理を行うことで大きな節税効果を得ることが可能です。適正な資産管理と会計処理を行うことで、節税効果を最大化し、財務基盤の強化につなげましょう。

- 役員に退職金を利用した節税方法
- 未払い費用の計上を利用した節税方法
- 別会社を設立して行う節税方法
- 売掛金の評価を利用した節税方法
- 中古車を使った節税方法
- 棚卸資産の評価損・廃棄計上を利用した節税方法
- 設備投資を中古機械にすることで実現できる節税方法
- 設備などの除却・廃棄を利用した節税方法
- 赤字の繰り越しを利用した節税方法
- 役員や従業員の社宅を使った節税方法
- 役員報酬の損金計上を使った節税方法
- HPデザインの発注を利用した節税方法
- 経営セーフティ共済を使った節税方法
- 家族への給与支給を利用した節税方法
- 経費の1年分前払いを利用した節税方法
- 健康診断を利用した節税方法
- 固定資産の資産計上細分化を利用した節税方法
- 決算賞与を活用した節税方法
- 採用費の前倒しを利用した節税方法
- 社員旅行を利用した節税方法
- 社会保険料の未払計上を利用した節税方法
- 社長自宅の買取を利用した節税方法
- 社内規定の整備のための外注費を利用した節税方法
- 出張手当を使った節税方法
- 小規模企業共済を使った節税方法
- 消耗品を決算前に購入して節税する方法
- 生命保険を活用した節税方法
サポートメニュー一覧
資金について相談したい!
会社設立について相談したい!
経営・税務会計について相談したい!
新着情報
-
2026/01/25
-
2026/01/18
-
2026/01/14
-
2026/01/07
-
2025/12/28