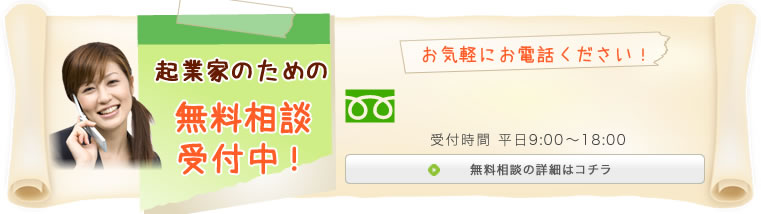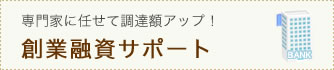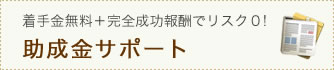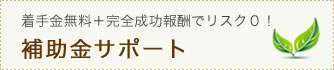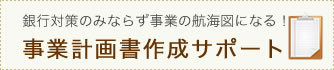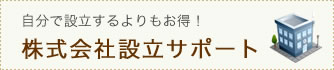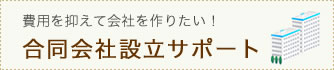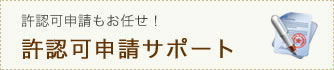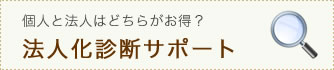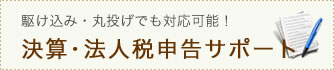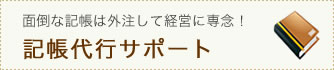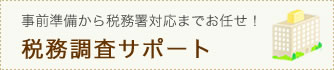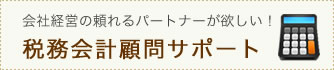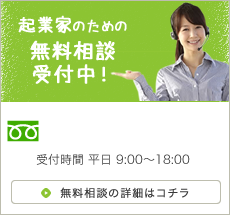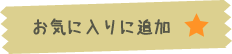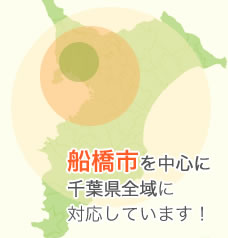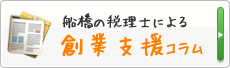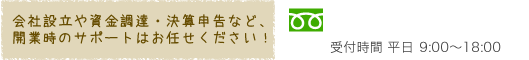出張手当を使った節税方法
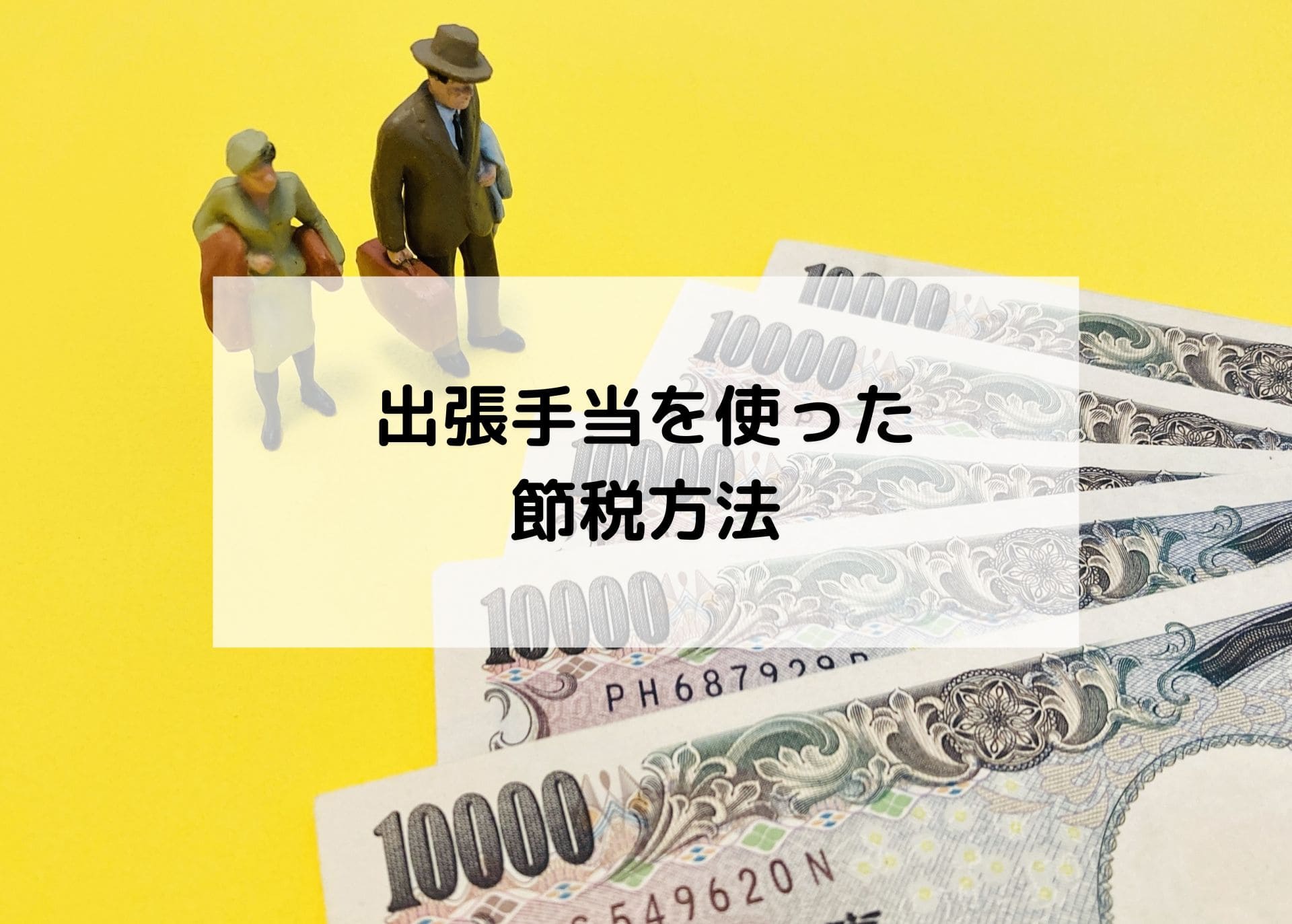
「出張手当」は、うまく活用することで合法的に節税が可能になる有効な手段の一つです。ここでは、出張手当を活用した節税方法について、仕組みや具体的な実践方法を詳しく解説します。
1. 出張手当とは?
出張手当とは、社員や役員が業務上の理由で出張をした際に支給される手当のことです。一般的には、出張時にかかる食費や交通費、宿泊費などを補填するために支給されます。
出張手当の目的:
・出張に伴う追加費用を補填する
・出張時の不便さや負担に対する補償
・出張中の諸経費の簡素化
この出張手当には、課税対象にならない範囲が存在します。この非課税枠を活用することで、合法的な節税が可能となります。
2. 出張手当の税務上の取り扱い
(1) 会社にとってのメリット
出張手当は会社の「損金(経費)」として計上可能であり損金に計上することで法人税の課税所得を減らせる
(2) 受け取る側(社員・役員)のメリット
・出張手当のうち、一定の基準額までは所得税が非課税になる
・社会保険料の算定基準となる給与には含まれないため、社会保険料負担も増えない
(3) 非課税となる条件
出張手当が非課税になるためには、以下の条件を満たす必要があります。
・出張手当の金額が「社会通念上妥当な範囲」であること
・実際に出張の事実があることを証明できること(出張報告書などが必要)
・会社の就業規則や給与規定に「出張手当」の規定があること
3. 出張手当を活用した節税方法
(1) 出張手当の金額を適切に設定する
出張手当は「社会通念上妥当な範囲」であれば非課税となります。
・一般的に「日当」として5,000円~10,000円程度が目安
・国内出張と海外出張で金額を分ける
・宿泊を伴う場合、宿泊費に加えて別途手当を設定する
【例】
・国内出張(宿泊なし):日当5,000円
・国内出張(宿泊あり):日当7,000円+宿泊手当3,000円
・海外出張(宿泊なし):日当8,000円
・海外出張(宿泊あり):日当10,000円+宿泊手当5,000円
(2) 出張報告書を作成し、証拠を残す
出張手当を経費計上するには、実際に出張が行われたことを証明する必要があります。そのために、以下のような出張報告書を作成します。
✅ 出張報告書に記載すべき項目
・出張日程
・出張先
・出張の目的
・業務内容
・出張先での成果
・添付資料(宿泊費や交通費の領収書)
税務調査が行われた際に出張の正当性を示す証拠になるため、報告書の管理は重要です。
(3) 役員にも出張手当を適用する
出張手当は、役員にも適用可能です。ただし、役員の場合は「社会通念上妥当な金額」であることがより重要となります。特に以下について気をつけてください。
・社員と役員で金額差をつけすぎない
・役員への出張手当も規程に明記しておく
(4) 出張手当を「給与」扱いにしない
出張手当を「給与」扱いにすると、所得税や社会保険料の負担が発生してしまいます。
・出張手当は就業規則や給与規定で「給与ではなく手当」として明記
・出張手当が課税対象とならないよう、金額の設定や運用を適切に行う
4. 出張手当を活用した節税シミュレーション
【例】
・社員10名が年間20回の国内出張(1泊)を行った場合
・出張手当:1回あたり日当5,000円+宿泊手当3,000円
⇒ 年間の出張手当総額
10名×20回×(5,000円+3,000円)=1,600,000円
この1,600,000円が損金扱いとなり、法人税の課税所得が減少
・法人税率を33%とした場合、
1,600,000円 × 33% = 528,000円 の節税効果
5. 出張手当活用時の注意点
出張手当を活用した節税を行う際には、以下の点に注意が必要です。
・実際に出張していない場合の虚偽申請は架空経費として重加算税の対象
・社会通念を超えた高額な出張手当は経費として認められない可能性
・出張手当に関連する領収書や証拠は必ず保管
・出張手当の規定が不明確だと税務調査で指摘を受ける可能性
6. まとめ
出張手当を上手に活用することで、企業にとっては法人税の節税効果、社員や役員にとっては所得税・社会保険料の負担軽減という二重のメリットが得られます。
・出張手当の金額を妥当な範囲で設定する
・出張報告書を作成し、証拠をきちんと管理する
・出張手当の取り扱いを就業規則や給与規定に明記する
出張手当をうまく使えば、毎年の税負担を大幅に減らすことが可能になります。適切な運用ルールを定めて、合法的かつ効果的な節税対策を実施しましょう。

- 役員に退職金を利用した節税方法
- 未払い費用の計上を利用した節税方法
- 別会社を設立して行う節税方法
- 売掛金の評価を利用した節税方法
- 中古車を使った節税方法
- 棚卸資産の評価損・廃棄計上を利用した節税方法
- 設備投資を中古機械にすることで実現できる節税方法
- 設備などの除却・廃棄を利用した節税方法
- 赤字の繰り越しを利用した節税方法
- 役員や従業員の社宅を使った節税方法
- 役員報酬の損金計上を使った節税方法
- HPデザインの発注を利用した節税方法
- 経営セーフティ共済を使った節税方法
- 家族への給与支給を利用した節税方法
- 経費の1年分前払いを利用した節税方法
- 健康診断を利用した節税方法
- 固定資産の資産計上細分化を利用した節税方法
- 決算賞与を活用した節税方法
- 採用費の前倒しを利用した節税方法
- 社員旅行を利用した節税方法
- 社会保険料の未払計上を利用した節税方法
- 社長自宅の買取を利用した節税方法
- 社内規定の整備のための外注費を利用した節税方法
- 出張手当を使った節税方法
- 小規模企業共済を使った節税方法
- 消耗品を決算前に購入して節税する方法
- 生命保険を活用した節税方法
サポートメニュー一覧
資金について相談したい!
会社設立について相談したい!
経営・税務会計について相談したい!
新着情報
-
2026/01/25
-
2026/01/18
-
2026/01/14
-
2026/01/07
-
2025/12/28