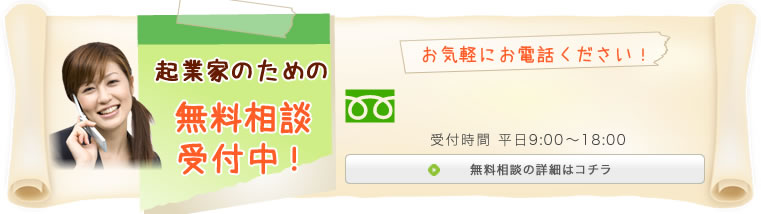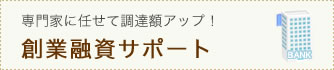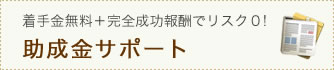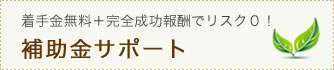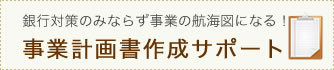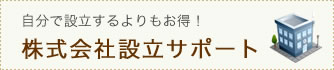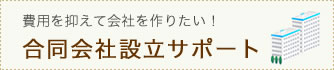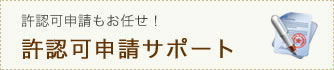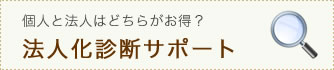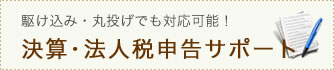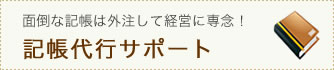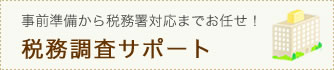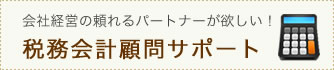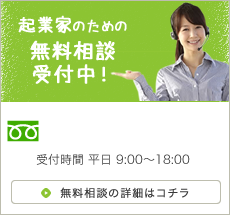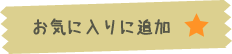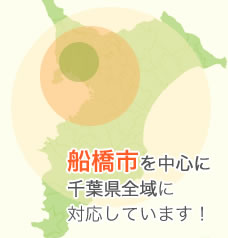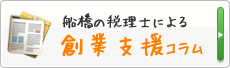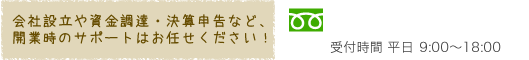役員や従業員の社宅を使った節税方法
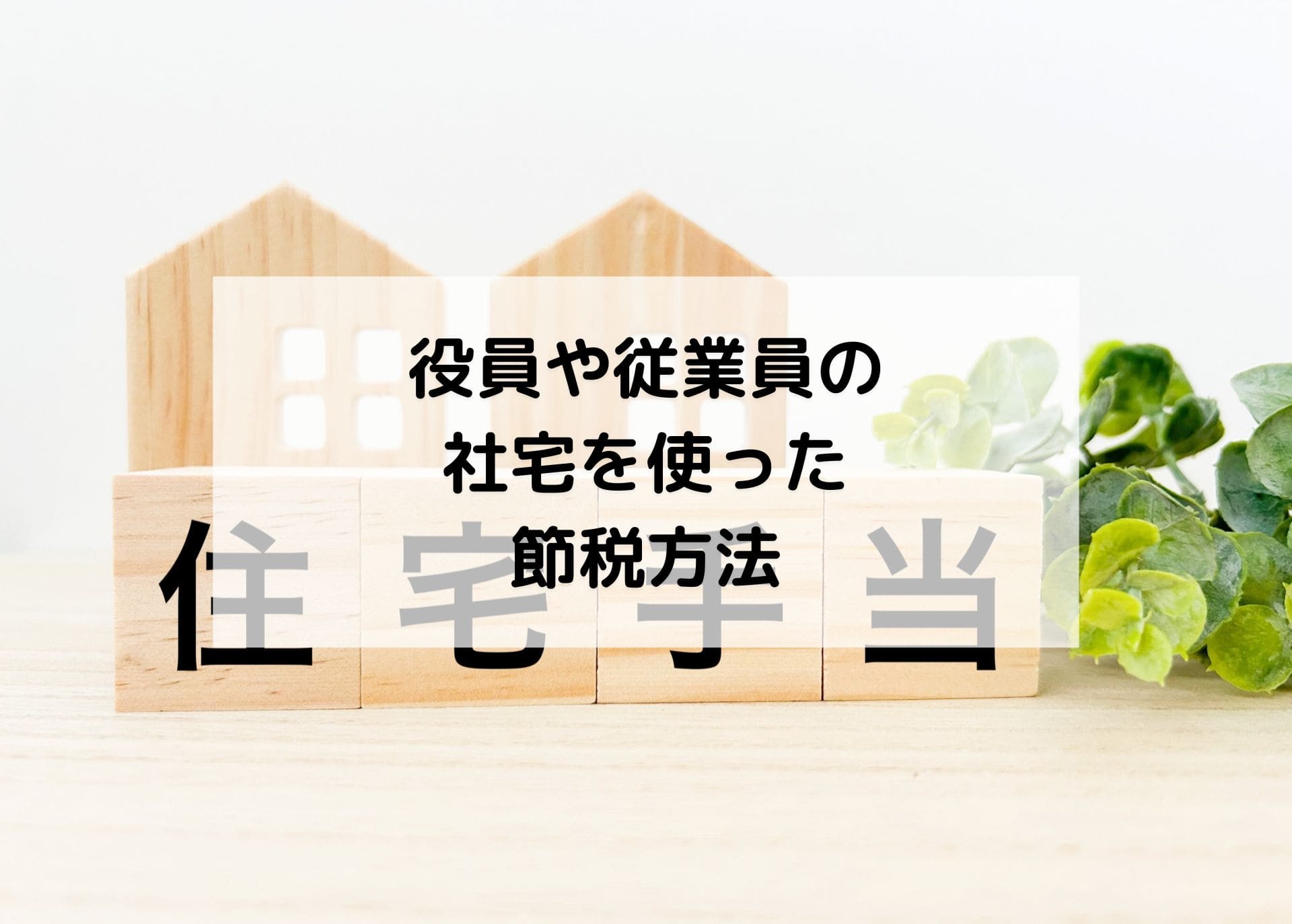
会社が役員や従業員に社宅を提供することで、法人税や所得税、社会保険料の負担を軽減し、節税効果を得ることが可能です。特に、役員社宅の場合は「給与扱い」とならないように適正な家賃設定や契約方法を工夫することで、大きな節税効果が期待できます。本記事では、役員や従業員に社宅を提供することによる節税効果や注意点について詳しく解説します。
1. 社宅を提供することで得られる節税効果
会社が役員や従業員に社宅を提供することで、以下のような節税効果があります。
(1) 会社側の節税効果
・社宅にかかる費用(家賃・修繕費・管理費・固定資産税など)はすべて会社の経費として計上可能
・経費計上により法人税が軽減される
・会社名義で契約・管理するため、会社資産として計上できる
(2) 役員・従業員側の節税効果
・社宅を「給与」ではなく「福利厚生」として提供できれば、所得税や社会保険料の対象外になる
・市場相場より低い家賃で住めるため、個人の支出負担が減少
・家賃補助を直接支給すると「給与扱い」となるが、社宅として提供すれば課税対象にならない
2. 従業員に社宅を提供する節税方法
(1) 給与課税されない社宅の条件
会社が従業員に無償または安価で社宅を提供した場合、以下のように計算された家賃が給与扱いにならず、課税対象から外れます。
給与課税されない家賃の算定式(国税庁基準)
家賃 = (建物の固定資産税評価額 × 0.2%) + (敷地の固定資産税評価額 × 0.22%) + (12円 × 延床面積(㎡))
例
・建物の固定資産税評価額:1,000万円
・土地の固定資産税評価額:2,000万円
・延床面積:100㎡
→ 家賃計算
(1,000万円 × 0.2%) + (2,000万円 × 0.22%) + (12円 × 100㎡) = 2万円 + 4.4万円 + 1,200円 = 65,200円
→ 従業員にこの金額以下で社宅を提供すれば給与課税対象外
(2) 従業員社宅の経費計上例
・家賃(固定資産税評価額に基づく)を5万円に設定
・会社が負担する社宅費用(家賃・修繕費・管理費)月額8万円
・役員の負担額:5万円
・差額3万円を「福利厚生費」として経費計上可能
→ 法人税の節税効果
・年間36万円(3万円 × 12ヶ月)を経費計上
・法人税(33%)で節税効果:約12万円
3. 役員に社宅を提供する節税方法
(1) 役員社宅の適正家賃の算定方法
役員社宅の場合、過度に安く提供すると「給与」と見なされるリスクがあるため、以下の基準で家賃を算定します。
小規模な住宅(床面積240㎡以下)の場合
家賃 = (建物の固定資産税評価額 × 0.2%) + (敷地の固定資産税評価額 × 0.22%) + (12円 × 延床面積(㎡))
大型住宅(床面積240㎡超)の場合
→ 時価の50%以上での家賃設定が必要
例
・建物の固定資産税評価額:2,000万円
・土地の固定資産税評価額:4,000万円
・延床面積:150㎡
→ 家賃計算
(2,000万円 × 0.2%) + (4,000万円 × 0.22%) + (12円 × 150㎡) = 4万円 + 8.8万円 + 1,800円 = 12.98万円
→ 14.98万円以下で設定すれば給与課税対象外
(2) 役員社宅の経費計上例
・社宅の適正家賃を15万円に設定
・会社が負担する社宅費用(家賃・修繕費・管理費)月額20万円
・役員の負担額:15万円
・差額5万円を「福利厚生費」として経費計上可能
→ 法人税の節税効果
・年間60万円(5万円 × 12ヶ月)を経費計上
・法人税(33%)で節税効果:約20万円
4. 社宅を使った節税の注意点
・家賃の設定
o 適正家賃を超えると「給与課税」扱いになる
・役員社宅の床面積
o 240㎡を超えると適正時価の50%以上の家賃が必要
・家賃負担のバランス
o 負担割合が極端だと「給与」と見なされる
5. まとめ
役員や従業員への社宅提供は、家賃や維持費を経費として計上することで法人税を軽減できる有効な節税手段です。適正な家賃設定を行い、役員社宅と従業員社宅の扱いを分けることで、給与課税を避けつつ、節税効果を最大化できます。また、社宅購入時の消費税還付や維持管理費の経費計上も併用することで、さらなる節税効果を得ることが可能です。

- 役員に退職金を利用した節税方法
- 未払い費用の計上を利用した節税方法
- 別会社を設立して行う節税方法
- 売掛金の評価を利用した節税方法
- 中古車を使った節税方法
- 棚卸資産の評価損・廃棄計上を利用した節税方法
- 設備投資を中古機械にすることで実現できる節税方法
- 設備などの除却・廃棄を利用した節税方法
- 赤字の繰り越しを利用した節税方法
- 役員や従業員の社宅を使った節税方法
- 役員報酬の損金計上を使った節税方法
- HPデザインの発注を利用した節税方法
- 経営セーフティ共済を使った節税方法
- 家族への給与支給を利用した節税方法
- 経費の1年分前払いを利用した節税方法
- 健康診断を利用した節税方法
- 固定資産の資産計上細分化を利用した節税方法
- 決算賞与を活用した節税方法
- 採用費の前倒しを利用した節税方法
- 社員旅行を利用した節税方法
- 社会保険料の未払計上を利用した節税方法
- 社長自宅の買取を利用した節税方法
- 社内規定の整備のための外注費を利用した節税方法
- 出張手当を使った節税方法
- 小規模企業共済を使った節税方法
- 消耗品を決算前に購入して節税する方法
- 生命保険を活用した節税方法
サポートメニュー一覧
資金について相談したい!
会社設立について相談したい!
経営・税務会計について相談したい!
新着情報
-
2026/01/25
-
2026/01/18
-
2026/01/14
-
2026/01/07
-
2025/12/28